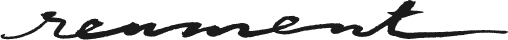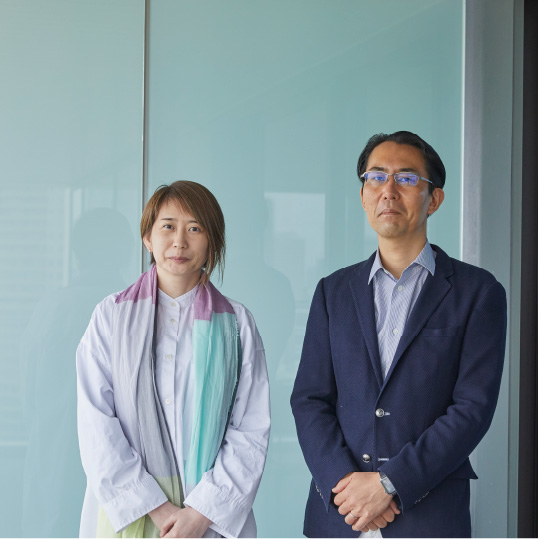JOURNAL
【対談・第三回】連綿とつむぐ、物語のはじまり。〜コットンへの想い、未来への願い、次の100年
renment[レンメント]というプロジェクトブランドが誕生した理由とは?そして近藤紡績所が発信していきたいコットンの真の面白さ、作り手たちへの想い、コットンの直面する課題、renmentがめざす先とは…対談の最終回、ますます濃い言葉が飛び出します。

コットンは、面白い
【梶原】斬新な機械で、一般的ではない作り方をしていますよね。概念を覆していくというか。
【近藤】watanomamaは、名前はフワッと優しいですけれど作る方は真剣勝負です。一個も不良品が出せないので。作り手側には、フワッとしていたら絶対できないぞ、という緊張感があります (笑)
——そんな作り方をしてるのは、世界でも近藤紡績所だけでしょうか?
【近藤】弊社だけでしょうね。このwatanomamaの製造方法も2021年3月末に特許が取れました。もっとも、あんなことをやろうと思う会社もなかったんだろうと思うのですが…。
【梶原】それに、紡績工場でなければできないことですよね?編み物メーカーだと、ちょっとできない範囲だと思いますし、双方の中間点にいるようなイメージです。もうひとつ私が感銘を受けたのは、良い糸を作るために「紡績している間に綿をできるだけ触らないようにする」ということ。糸を運ぶときにも触らないで運べる方法や、あらゆる機械も工夫がされていて、実は触れなければ触れないほど品質が良くなるということも初めて知りました。この上質な糸ひとつ作るにも、繊細にストイックに努力されているのですね。


【近藤】そうです。我々が糸を作る工程でもいろいろありますが、この糸を使っていただいている取引先にも、まだ知られていないもの凄いこだわりや工夫がたくさんあるんです。そういうことをなかなか発信できなかったのですが、これからは作り手の方々の想いも一緒に発信しながら歩んでいきたいんです、このrenmentという場で。たとえば機屋さんや、ニッターさんと組んで新しいモノができて、それを知った消費者やアパレルの方が「こんなことができるんだ、すごい」と盛り上がっていけば、直接的に我々の利益にはならなくとも、日本の繊維やものづくりの利益になるのでは。renmentは、モノを売る場でありながらそういう想いや情報を発信することのできるブランド、というよりもプロジェクトでありたいと思っています。
【梶原】たしかに。「こんなことできるんだ、すごい」と、初めてwatanomamaに触れた瞬間、驚きました。コットンとは思えない薄さと軽さで。今までたくさんの素材に触ってきたけれど、まだまだ気づかされるものがあるということに嬉しくなりましたし、感銘を受けましたね。
【近藤】こちらの生地(海島綿)は、本当に自分たちが作りたかったものです。一方こちらの生地(watanomama)はこんなものになるとは想像していなかった。
【梶原】繊維の面白さというのは、ちょっとしたことでものすごく化けること。組織、密度、加工など工程の組み合わせ方で様々な個性が引き出せます。世界の素材を想像した幅広い視点で海島綿とwatanomamaを見ると、一見違う個性を持ちながらも、どこか似ている世界観があります。ストイックだけど柔らかな雰囲気で上品で丁寧な感覚に近藤紡績所らしさを感じます。私、仕事柄いろいろなパジャマを持っているんですけど、watanomamaは心地良くて、このパジャマを選んで着る確率が高いです。
——このホテル(メズム東京)で採用されているローブも近藤紡績所の?
【近藤】ええ、そうですね、watanomamaではありませんが。ホテルリネンには、クリーニングの工程の為に、伸びたり縮んだりしない織物が常識でした。しかし、それでは、寝返りを打った時に突っ張って目が覚めてしまうことがあるので、それを防ぐためにサイズがゆとりのあるサイズになっていることが多いのです。我々は、長年肌着用のニット糸を主に作って参りましたので、綿の良さ・ニットの良さを損なわずに工業洗濯に耐えられるようにしました。おそらくホテル業界初だと思いますけれども。綿の良さを生かしつつ、工業用洗濯(80℃~90℃)で洗って乾燥させるのには繊維に相当なストレスがかかるのですが、プレス機で絞って思いっきりプレスで押し付けて…と、非常に過酷です。ですから、普通なら馬鹿げてやらないようなものですが、こちらの支配人がご自身で本当に良いと思うものをこだわって作られているそうで、選んでいただいてありがたいです。いろいろなトライアンドエラーをしましたが、結果的に採用していただけるなんて。
——普通の人ではやらない、馬鹿げたこと。かっこいいです。
【近藤】馬鹿げたもので終わっちゃうといけませんが、出会いがあってよかったです。ホテル業界でどこも採用していなかったニットパジャマを採用して頂いたメズム東京様、そして非常に扱いにくい素材にも関わらず、試験を繰り返して、工業的に洗濯できるようにしていただいた、リネン業者である新日本ウエックス様との出会いがあったからこそだと思っています。自分一人、一社だけではできないことが、そういった想いを持った人々が集まることで、新たな驚きや感動を生み出せるようなプロジェクトにしていきたいと思っています。
【梶原】これからも広がっていけばいいですよね。人とのつながりが、連綿と。

【近藤】はい、我々が知らないといけないこともいっぱいあると思います。やはり、環境とどう付き合っていくかは避けては通れないです。紡績業はかなり電力を使うので。だからと言って、CO2フリーの発電だけですべての工場が賄えるかというと、日本の火力発電に多くを依存する電源構成から、電気代が3割から4割くらい上がってしまうので、全部を取り入れることはなかなか難しいというのが現実です。しかし、この比率を徐々に高めていくこともやっていきたいと思っています。綿も天然の繊維ですので温暖化が進むといずれは取れなくなってしまうとか、心配もあるわけです。我々の大町工場も冷たい地下水を使わせていただいているんですけれど、雪が降らなかったら地下水も出てこなくなってしまうので。
——なるほど、綿栽培も気候変動と密接な関係にありますね。
【近藤】カリブで作っている綿なんかも、海面が上昇したりハリケーンが多発したりすると採れなくなる場所もあるわけですから。環境問題や気候変動に対して、我々は何ができるのか。私も、会社も、消費者の方も、地球にいる人間としてどんなことができるだろうと、考えていかなければならない。まだ分かっていないことも色々ありますけれど、環境と向き合いつつ、お客さまにどうやって気持ちのいい綿製品をお届けするか。
オーガニックも理想として素晴らしいとは思いますけれど、オーガニックだけで世界中の人々に綿製品を届けられるのか、食料がいきわたるのか、というと、そういうわけにもいかないので……そのバランスですよね。どんどん環境を壊してまで綿を作っていいとは思わないですけど、オーガニックだけでも足りない。持続可能な世界に向けて、我々自身ももっと学んでいかないといけない。renmentの認知度が高まっていけば、みなさまのご意見も広く承れるようになりますし、繊維が抱える課題を一緒に考えていきたいなと思っています。
——伝えたいことをちゃんと伝わるようにするためのプラットホームとしての役割も大切ですね。
【近藤】私が小さい頃は30年後には石油が無くなると言われていて、車にも乗れなくなると心配していました。今もCO2問題についてみんなで心配していますけれど、人類が英知を絞ればなんとか克服していけるのでは、悲劇的な結末にはならないんじゃないか、世の中より良くなっていけるんじゃないかと私は思っているのです。綿製品に携わるものとして、綿を作ることだとか、糸を作る工程で、自分たちにできることで貢献していきたいと思っています。まだ何ができることなのかは、正解は分からず考えつづけている状態ですけれども。
【梶原】何をするべきか考えつづけるからこその明確さがあると思います。多分社員のみなさんも、外部で関わっている私たちも、その明確な想いに共感して、一緒に追求していきたいと思えるんですね。
——課題はあるけど、未来はそんなに悪くない。
【近藤】と、思ってますね。かつての綿の栽培や紡績の歴史を紐解くと、プランテーションで綿を作って、産業革命が起こって、毛紡績や綿紡績が始まった。その影には奴隷がいたり、環境破壊があったり、労働者の劣悪な環境があったりしたことは無視できません。日本でも、女工哀史のように、紡績工場の環境が劣悪だった歴史もありました……昔は中学を卒業した地方からの人が千人単位二千人単位で働いている時代もありました。、その時に全く問題がなかったとは断言できないですし、それこそ、パワハラやセクハラもあったかもしれません。ですが、大きな時の流れの中で、工員さんたちが働きながら高校に行って、高校の資格を取って、家庭に戻られたわけですけれども、その方たちのお子さんっていうのは、普通の高校を出たり、大学を出たり、親の世代より良くなってきているとも思います。環境問題も、日本はでは四日市喘息など公害もありましたけれど、今では空気も非常にきれいになって窓を開けて話しができています。さまざまなショッキングな本が売れたりもするんですけれども、私は、基本的に世の中は……常に新しい課題はどんどん出てきますけれど……長い目で見るとより良くなってきている思いがあります。環境についても、今までのように好き勝手やっていてはなりませんが、人類全体としては乗り越えていけると思っていますし、乗り越えていかなきゃいけない。世の中には人それぞれ、会社それぞれ、役目があると思っていますので、その中で我々は、ものづくりをしながら役割を果たしていきたいと思っています。
——現実は厳しいけれど、そこに希望が感じられるのは、モノや人を育てていらっしゃる方だからでしょうか。綿を作る、糸をつむぐ、編む、織る、染める、あらゆる人の存在を横に感じているから、悲観的になってる場合じゃないのかもしれません。希望の場所ですね、renmentは。
【近藤】何でもかんでも、簡単でバラ色だとは思っていないです。規制や制限など我慢しなければいけないことが当然あると思いますけれど、そのなかでも世の中はよくなってきたと思ってますし、これからもより良くなれると思っています。

【梶原】新日常が生まれている実感があります。普通にあたりまえにあったことが、あたりまえじゃなくなるということを世界中が同時に体験し、価値観の変化が加速化したと思います。気づく、見直す、立ち戻る。そして日常に感謝する気持ちが芽生えやすくなったと思いますね。同様に、コットンもいつもあたりまえのようにある、永遠にある。コットンの先なんて考えなくても必ずそこにある。という存在だったのが、気候変動によって努力をしなければ失われる可能性がある。毎日心地よいと思って身に着けているものが、100年後に同じようにあるとは限らないと、気がつきやすいタイミングになったとは思います。コロナも、ある種の警鐘だと思いますし。
【近藤】あたりまえだと思っていたことが、如何に有難いことだったかに気づきましたね。『ホモデウス(ユヴァル・ノア・ハラリの著書)』か、あの本の中ではパンデミックは克服したみたいなことを冒頭に書いていましたけど、現実起こってしまったわけですよね。ただ、不幸中の幸いだったのは、もし、これが数十年前に起こっていたら人類は成す術無く、DNAの解析は現代のように進まず、ワクチンもすぐには作られず、リモートワークも出来なかった。そういう意味ではある意味人類はギリギリ最悪の時ではなかったのかもしれません。今のままでは、より良くなる前にこの世界が終わってしまうよっていう警告なのかとも感じるのです。
【梶原】あたりまえだと思っていたことに気づく、グレートリセットのときですよね。コロナの前から、10年後、30年後の気温上昇にともなう環境の変化について欧米ではディスカッションが活発でした。テキスタイルの商談でも真剣にリサイクルの開発や素材のトレーサビリティについて話をしていましたが、日本を含めアジアではまだ情報が少なく個々の危機感は薄い印象でした。ただこのパンデミックが世界で同時に起こり、人の動きが停止することで自然環境が回復することを実感した人は多かったと思います。
——今までずっと変えたいなと思っていたけど、なあなあで来ていたこと。それを変えるタイミング。
【梶原】生活も、モノづくりも、ゴミ廃棄のことも、ますます問題意識が高まっていくと思います。
これから、人と自然の関わり方を試行錯誤しながらデジタルを活用した暮らしのバランスが益々追求されていくのではないかと思います。

【梶原】初めて触ります…海島綿の印象をそのまま形にしたような滑らか感とツヤ感ですね。絶対的な個性があるのですが、かつ軽さも感じる。海島綿ってなんで軽さを感じるんでしょうね。非常にキレがいい感じ。
【近藤】ちょっとだけタネ明かしをさせていただくと、糊をつけずにシャトル織機でゆっくりゆっくり丁寧に仕上げています。シルケット(アルカリで膨潤させる加工法)とか、そういうことはしていない。シルケットをすると繊維がふわっと膨らむんで、ふっくら感がでて、誤魔化せてしまうんですけど、これはあえて何にもしてない。料理にお塩だけつけて、いただく感じです。
【梶原】やっぱりストイックですね…。柔らかいし、艶やかだし、よくわからない人が触れても素だとは思わないですね。
【近藤】素じゃないと、見た目はいいんだけれども化繊と同じような感じになってしまって。
【近藤】話を元に戻しますと、renmentをどんな場にしたいかということですが。織機を織っている機屋さんや、加工している染色工場の方たち、さまざまな作り手たちが「こんなものを作れたらいいね」とか「これを作ったらワクワクするね」という想いを寄せ合って仕事が生まれる場にもなるとといい。「大変なことでも、面白そうならやってみよう」という想いのある人たちに集まっていただきたい。何より、それをお客さまに知っていただきたい。ここから新しいものを生み出して、心に訴えかけるようなものを作っていきたいのです。環境の問題だとかも考えていきたい。ちなみに私、お酒は強くないんですけど、利き酒は好きでして…利き酒をすると味の違いがわかるじゃないですか。繊維に関しても、加工したもの加工してないもの、さらに全然違うものなどを比べて体験していただけたらいいなと思います。


【梶原】これはwatanomamaの生機を加工しています。概念を打ち破るような真逆の視点をもった開発も、ときに意外な効果を生み出す可能性があります。そこから、次の発展の道も見つかるのではないかと思います。
【近藤】やっぱりみなさまがワクワクするようなものを作っていきたい。もっとやってやろう、とスイッチが入るようなものを。機械と人間が違うのは、機械はとにかく淡々と与えられたことをやるけれど、人間は、時に失敗したり、気分が乗らないとこともあったりしますが、きついけど頑張ろうとか、ここにいる人たちとつながって一緒にやりたい、という想いは機械ではなく人間だからこそだと思っています。今はコロナの状況でなかなか現場には行けませんが、落ち着いたら工場の現場で作っている工程だとか、使っていただいているみなさんで、是非つながってもらいたいと思ってますね。
【梶原】近藤社長をもっともっといろいろ人に知ってもらいたいんです、私としては。一番想いがある方の言葉をコットンが好きな方々に繋げていきたいです。モノづくりに携わる方々が想いを発信していくことは、日本がテキスタイル産業を活性化し継続していくために、これからもっと大事になると思います。
【近藤】私は、本当は人前に出るのが得意ではなくて…でもやっぱり伝えなくちゃいけないと。それが私の仕事であると思うし、若い人たちにも伝えていきたいと思ってます。
(おわり)
近藤大揮
(株式会社 近藤紡績所 代表取締役 社長)
ブランドアドバイザー 梶原加奈子
(株式会社KAJIHARA DESIGN STUDIO 代表取締役 社長)
http://www.kajihara-design.com
【対談・第三回】連綿とつむぐ、物語のはじまり。
Date: 11.6.2021
Text: Mika Kunii
Photo: Daisuke Mizushima
Special Thanks: mesm Tokyo
RECENT JOURNAL
-
Column
【つなげていく人】企業の垣根を超え、仲間と共に新しいモノづくりに挑戦する「今治タオル青年部会」の記録。
愛媛県今治市は約120年間、タオルづくりの聖地として、タオル産業の発展を担ってきた。その背景には、若手後継者で構成された「今治タオル青年部会」の存在がある。代々受け継がれるタオル産業の未来を担う青年部会の取り組みと共に、青年部会が今回コットンの最高峰と言われるカリブ産シーアイランドコットンを使い、とことんこだわりを持って作った“ おんまくええタオル”を合せて紹介していく。
-
Interview
【つなげていく人】博物館級の旧式機械で生地を織り上げる鈴木利幸織布工場のモノづくりのポリシーとは…
静岡県 浜松市を含む遠州地域は古くから綿織物が盛んで「繊維のまち」といわれ、今でも他にはない特徴的な織物をつくる工場が多く残っています。その土地で技術や経験を活かして、敢えて旧式の機械を使い、生産性にこだわらない上質な織物をつくり続けている鈴木利幸織布工場の鈴木利幸社長 。どのようなこだわりや想いを持って仕事を続けてこられたかを実際に工場を訪問してお話をお伺いしてきました。
-
Interview
【つなげていく人】
鐘と太鼓の音響く徳島。
縫製技術の継承で紡がれる、
想いのリレー。今回お話を伺った斎川千浪さんは、renmentのTシャツやパーカーを縫製しているKSプランニング徳島工場で、長く縫製の技術を数多くの人に指導してきました。生まれも育ちも生粋の徳島っ子の斎川さんに、徳島の魅力、お仕事をされる上で大切にしていることについて、お話を伺いました。
-
Interview
【想いをつなげる】信州の雄大な自然の美しさ、動植物と人々の暮らし。レンズを通して感じる大町市の愉しみ方とは…
本サイトのトップページに使用されている、朝焼けに照らされる雄大な北アルプス連山の写真。撮影されたのは、近藤紡績所大町工場で工務課長を務められる大島啓(おおしまあきら)さん。今回は、renmentの糸が紡がれる長野県大町市の魅力について、趣味のカメラを通して大町の魅力を誰よりもよく知る大島さんに、お話を伺った。
-
Interview
【想いをつなげる】美しい北アルプスに囲まれた雪国、信州の大町市で綿花畑に挑戦しつづける人の物語。
現在の日本では数少ない「綿」を中心とした紡績工場が長野県大町市にある。古き良き技術と最先端の技術の両方を活かした糸づくりを続けるこの工場では、数年前から敷地内の一角に綿花畑を設け、毎年少ないながらも綿花の収穫を行ってきた。なぜ、この地に綿花畑が作られたのか。綿花畑で何が芽生え、実ってきたのか。畑の守り人でもある近藤紡績所 大町工場の一志(いっし)勉さんにお話をうかがった。
-
Interview
【対談・第三回】連綿とつむぐ、物語のはじまり。〜コットンへの想い、未来への願い、次の100年
renment[レンメント]というプロジェクトブランドが誕生した理由とは?そして近藤紡績所が発信していきたいコットンの真の面白さ、作り手たちへの想い、コットンの直面する課題、renmentがめざす先とは…対談の最終回、ますます濃い言葉が飛び出します。